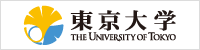【報告】CPAG若手ワークショップ「普遍をめぐる問い――18~20世紀東アジアから考える」
2015年2月7日(土)、東洋文化研究所第一会議室にて、CPAG若手ワークショップ「普遍をめぐる問い――18~20世紀東アジアから考える」が開催された。本ワークショップは今年度CPAG特任研究員の新居洋子が企画したものである。以下、新居の視点から会全体を振り返ることによって、企画者としての最後の責務を果たしたい。
「普遍をめぐる問い」とは、今にして思えば大上段に振りかぶりすぎた表題だが、いちスタッフである点では内部者として、また元来歴史学徒であるという点では外部者としてCPAGに関わってきた、私なりの格闘の成果を込めたつもりである。CPAG、すなわち「グローバル化時代における現代思想――概念マップの再構築(Contemporary Philosophy in the Age of Globalization)」は2012年度に開始し、今年度をもって一旦終了を迎える。その間一貫して、現代思想(主に20世紀思想)を基盤としつつ、グローバル化時代にふさわしい「新しい普遍」を創出する、というテーマを掲げてきた。今年度は国際シンポジウム「“現場”の挑戦と文学の営み」(6月)、そしてラップアップシンポジウム「“新しい普遍性”をめぐる東アジア三方対話」(11月)などを主催し、東アジア各国を中心とする世界各機関の研究者を招聘した。これらの場では、「新天下主義」(許紀霖教授)などの斬新な着想をめぐって白熱した論争が繰り広げられ、現在と未来にふさわしい「新しい普遍」とは何かについて真摯な議論が展開された。
こうしたCPAGの挑戦を、私なりに批判的に継承するとすれば、CPAGを歴史化してみるということに尽きる。すなわち「新しい普遍」の探究を、近代、現代に特権的な事象とするのではなく、全時代的に絶えず存在してきた「普遍的なるもの」の追求の歴史のなかに位置づけてみる、ということである。普遍とは、恐らく「事実としては」存在しないかもしれない。しかし絶えざる「問い」として、探究の過程として、普遍はそれこそ普遍的に存在する。なんとなく業のようにも思える。また普遍の探究は、しばしば他を我に取り込むという側面を持つことから、近現代に限らず前近代においても、グローバル化とそれに伴う他者の発見と歩を一にして進展した。これはともすれば、他者との一体化への欲求と不可分であり、暴力による強制を伴うことから、時として様々な悲劇をも生んできた。こうした事実にも関わらず、今後も様々な困難に遭遇しつつ継続していくであろう「新しい普遍」の追求と挑戦の歴史を、実証に基づいて批判的に叙述すること、これが今回私の立てた主な課題である。なお私自身の専門との関わりから、今回は東アジアを対象とし、特に前近代と近代の両方を含む18~20世紀前半における事象を中心とした。
この課題に共に取り組んでもらうべく、気鋭の若手研究者四人に報告をお願いした。私を含む五人の専門はほとんどバラバラで、専門は文史哲の三領域にまたがり、対象も前近代と近代、そして日本、中国、朝鮮、ヨーロッパの各地域にわたる。そのため当初は、全体としての一貫性に一抹の不安があったが、結果として第一部は前近代東アジアおよびヨーロッパにおける朱子学の普遍性をめぐる問題、第二部は中国の近代化において伝統という旧来の普遍が果たした役割をいかに評価するかという問題に収斂する形となり、終始良い流れで議論が進んだように思う。以下、新居の視点から全報告の概要を紹介するが、浅学ゆえの誤解の可能性を免れない。ご関心の向きは是非各報告者の著作も、併せて参照されたい。
周知の如く東アジア各国では、南宋中国に確立された朱子学が、その後基本的には19世紀まで正統教学としての位置を占めたが、こうした朱子学のいわば普遍化は、相対化への強い志向をも生み出した。18世紀を中心として、朱子学に対する反省、相対化の動きが活発化し、そのなかで中国では陽明学、清朝考証学、朝鮮では実学(北学)、そして江戸期日本ではいわゆる古学が勃興した。第一部を構成する高山報告、金光來報告、新居報告は、それぞれこの朱子学の正統化ならびに相対化という、前近代東アジア思想史を構成する中心的問題と密接に関連している。
第一報告は、高山大毅氏(東京大学)の「徂徠学以後の「道」と「聖人」―江戸中期における中国の相対化をめぐって―」である。江戸期古学の代表的学派たる徂徠学の思想的、歴史的意義については既に、講談社学術文庫版の荻生徂徠『政談』に収められた高山氏の解説に詳しいが、今回の氏の報告は、徂徠学において朱子学の重要概念たる「聖人」と「道」の相対化を通じて、いかに中国そのものが相対化されたかという問題に焦点をあて、この朱子学と中国の相対化がさらに世界観の転換へと繋がった可能性までも示唆した。高山氏によれば「聖人」とは、朱子学では全ての人々にとって「学びて至るべき」存在(但し、そこに女性が含まれるか否かといった問題は残されているという)、すなわち共通して備わった道徳規範を発揮すれば到達し得るものであるのに対し、徂徠学では「統治機構を制定した王朝の創始者」、すなわち堯舜湯文武などの各「開国の君」を指す。また「道」とは、朱子学では事物当行の「理」=基本的には「形而上」のものであるのに対し、徂徠学では「聖人」の設けた礼楽刑政などの「具体的な統治機構の集合体」を指す。

こうした「聖人」観、「道」観の根本的転換は、「史」の重視を背景とした徂徠学の「復古」的学問体系の構築に由来し、古今中国の間に決定的な断絶を置く見方、すなわち理想的な古代中国/没落した後代中国とする歴史観と連関している。こうした徂徠学者の認識はやがて、中国の外、すなわち「泰平」を実現した徳川政権の治世における「聖人」および「道」の発見を生み出す。さらに彼らは、より外、すなわち西洋諸国に対しても大きな注意を払うに至っている。
以上、高山氏によって鮮明に描き出された徂徠学者の思想的挑戦は、旧来の朱子学および中国という普遍の相対化を出発点として、やがて新たに構築された「聖人」や「道」を普遍化するという試みまでも含んでいる。これを、普遍をめぐる様々な方向の問いが織り合わさったものとしてみることも可能だろう。その背景には恐らく、鎖国によって同時代中国(清朝)に対する理解が相対的に狭まり、その一方でオランダとの交流によって西洋に関する知識が輸入され、日本の外に対する視野が限定的ながら拡大するという、いわばグローバル化とその逆が同時進行していくような、複雑な江戸期日本の情勢が関わっていたと推測される。
ところで徂徠学は「利用厚生」をうたうなど、同時期に勃興した朝鮮実学(北学)との共通点を多く持つ。但し朝鮮実学は、どちらかといえば朱子学内部から発した相対化の運きであり、その意味で明清代中国の朱子学者が盛んに掲げた「実学」に似る。16世紀末以降、中国に滞在したイエズス会宣教師(在華イエズス会士)を媒介として、「西学」すなわちヨーロッパの思想や自然科学が中国、朝鮮に伝播したが、いずれにおいても、この西学の主な受容者は「実学」を掲げる朱子学者だった(例えば同時期中国で隆盛したとされる陽明学にしても、管見の限り、ほとんど西学との交渉を持たなかったようである)。
こうした、朱子学が持つある種の柔軟性は、様々な批判を受けつつも19世紀まで正統教学としての命脈を保った、一つの要因といえるかもしれない。第二報告、金光来氏(東京大学)の「性理学と霊魂論――慎後聃の西欧霊魂論批判から見えるもの」は、壬辰倭乱(文禄の役)&丙子胡乱による朝鮮社会の変動、中国における明清交替などを背景に、いわゆる小中華主義とともに濃厚化する朱子学的環境、その一方で強まる「実学」的気風のなか、朝鮮朱子学者が西学といかなる対話を繰り広げたかという問題に焦点を当てた。
金氏の報告は、慎後聃による西学批判を中心とする。慎後聃は、幾湖南人の系列に属する有名な李瀷の弟子で、『遯窩西学弁』を著し、主に朱子性理学的立場からの西学批判を展開した。この著作において、まず唯一最高の神による天地創造というキリスト教的創造論や、霊魂不滅説は、それぞれ朱子学的理気論と魂魄説の立場から全面拒否された。また恩寵説や理性/啓示説は、あくまで「人間の志力」と「理」に最大限の信頼を置く朱子学的人間論によって反対された。

但し、慎後聃は以上の如く、スコラ神学的内容に対しては「一笑に付している」のに対し、哲学的内容については真剣かつ周到な批判を繰り広げている。西学書は、スコラ哲学の立場から、認識のプロセスを「五司」(五官)⇒「公司」(共通感覚)⇒「思司」(表象力)⇒「明悟」(理性)という各段階に区分し、さらに表象力と理性の間に「記含」(記憶)を置く。また記憶は感覚的記憶/理性的記憶に、認識対象は感覚的知覚/理性的認識に区分される。こうした精神活動の段階、および感覚/理性の区分に対し、慎後聃は心=「記蔵、思惟、酬酢、云為する所以」の全ての主宰とする心性論との矛盾を説いた。
理性に関しても、能動/受動を分け、能動的理性が「万像」(理性的現像)を作り、受動的理性=それに光明を加える⇒万物を悟るとする区分に対し、それぞれ理気論と心性論を適用し存在を否定した。最後に欲求に関して、慎後聃は「司欲」(感覚的欲求)/霊欲(理性的欲求)の区分を、朱子学の人心/道心に似るという比較的穏当な理解をみせ、「もっとも対話の余地のある内容であった」。しかし西学書では、感覚的欲求が随うところの表象力/本能が「思司」/「性」と訳され、朱子学的「心思」/「性」との深刻な分岐のため、慎後聃の理解は遮られ、否定という結果を生んだ。
以上、金光来氏が明らかにした慎後聃による西学批判は、一見私が述べた朱子学の柔軟性ということと矛盾するかもしれない。しかし、金氏は結論として「結局両者の対話は、認識論的伝統の相違や言語の壁によって遮られたものの、慎後聃自らが学術的批評の対象としているのは普遍性をもつと認められる事柄であり、朝鮮の性理学者、慎後聃の学問的関心は、まさにそこにあった」と述べた。これは大変注目すべき議論と私は考える。つまり批判もある意味では対話の一形態であり、互いの思想の核心が触れ合ったからこそ受容も批判も可能となり、その意味で普遍的なるものをめぐる対話が成立したのだといえよう。
金報告が取り上げたのは、朱子学の側からみたヨーロッパの思想だった。第三報告、新居洋子(東洋文化研究所CPAG)の「18世紀ヨーロッパ科学/偽科学と陰陽理論」は、その逆の事象を対象とする。16~18世紀末、ヨーロッパにおける中国情報の最も主要な供給者は、在華イエズス会士だった。彼らは「適応政策(Accomodatio)」と呼ばれる独特の宣教戦略のもと、特に儒教について相当精密な研究を展開し、儒教経書に現れる「上帝」や「天」=カトリックの神としたり(天主上帝説)、儒教とカトリックの同質性を説いたり(補儒論)したが、同じ儒教でありながら、同時代中国における正統儒教の位置にあった朱子学は、長らく否定の対象だった。初期、すなわち16~17世紀の在華イエズス会士にとって、朱子学的理気論は、人格と知性を持つ最高存在=神を最上位に置くカトリック的万物生成観からすれば、到底「適応」不可能な存在でしかなかった。彼らは朱子学者を「無神論者」と呼び、また太極や理、陰陽を質料、形相、熱(calor)&冷(frio)、普遍的動力因といったスコラ哲学的概念に置き換え、もっぱら物質的側面においてのみ捉えた。

この状況に転回が生じるのは18世紀で、まず前半には在華イエズス会士プレマール(Prémare)と、在華イエズス会士の文通相手だったライプニッツ(Leibniz)が、17世紀とは全く違う、かつ大胆な解釈を試みる。まずプレマールは、理気二元論は誤りで、太極&理、陰、陽=三位一体説の象徴であり、上古中国が原始キリスト教の教義を有した証拠だという、フィギュリスト的解釈を施した。またライプニッツの理気論解釈は、明らかに彼独自の予定調和的モナド論によって練り上げられ、理&太極(上帝)=神=諸物を生み出し、完成形(予定された秩序が内蔵する)を与える、とする。
これに対しさらなる転回を加えたのが、18世紀後半の在華イエズス会士アミオ(Amiot)である。アミオの理気論に関する報告において顕著なのは、理気論を構成する諸概念=太極、理、陰陽などが、しばしばメスメリズム(mesmérisme)やニュートン科学における諸概念=流体、動物磁気、両極、微粒子、引力などと置換される点である。様々な史料からすると、当時アミオは、ヨーロッパにおいて科学/偽科学のはざまに置かれ、王権やアカデミズムから激しい弾劾を受けていたメスメリズムの支持者から、その有効性を示す証拠を中国で調査するよう、依頼を受けていた可能性が高い。さらに理=引力の未知の原理とし、「ニュートン学派の人々、および古今全ての引力説論者」にとって有益だろうと述べている。アミオは太極、理、陰陽を物質として捉え、またその解釈には多分にスコラ哲学的概念が入り混じるため、初期の在華イエズス会士と似るが、大きな分岐が存在するのはアミオが太極の上に神を接続した点である。カトリックのアミオにとって、神の接続は理気論を肯定するためのいわば下準備であり、理気論本体をめぐる議論は、それがいかにヨーロッパ諸科学を補完し、「自然に関する真実」の解明に寄与し得るか、という問題に重点を移したといえる。
以上の如く、在華イエズス会士(&ライプニッツ)における朱子学理解は、常に同時代の普遍性を体現する、もしくは普遍性の獲得を目指す諸思想との対話/対決のなかで練り上げられた。こうした理解は、さらに同時代ヨーロッパで在華イエズス会士の報告が多数出版されることによって広範に流通し、ヨーロッパ知識人における中国理解の基盤を形成した。こうした、在華イエズス会士を媒介とした中国思想のヨーロッパへの伝播は、前近代の時点で、非常に局地的ながら東アジアの側からのグローバル化が、(モノやヒトのみならず)思想という領域においても着実に展開していたことを示す、貴重な事例といえる。
以上が第一部の概略である。続く第二部は、主に「現場」の視点から、19~20世紀中国における伝統と近代の相克/相生を捉え直すという主旨を掲げ、実践の次元で追求された普遍性とはいかなるものか、検討した。第二部は、第四報告、曺貞恩氏(慶熙大学)の「中医との出会い――医療宣教師の中国伝統医学に対する認識」から始まった。曺氏によれば、19世紀以降、プロテスタント教会は医療伝道の必要性から、医師を医療宣教師という肩書きで非キリスト教世界へ派遣した、という。清末中国に到来した医療宣教師にとって、中国伝統医学にどう対応するかは常に大きな課題であり続けた。従来の研究は、医療宣教師が中医に対し、一定程度「同情」あるいは肯定的態度を見せた点を強調するが、こうした態度から直ちに宣教師の中医に対する高評価を導き出すことは果たして妥当なのか。この問題から出発した曺氏は、まず初期の医療宣教師のなかに、中医を非科学的などと断じる否定的態度と、一定の有効性を認める肯定的態度が共存したことを確認した。後者に関しては特に、西薬不足という現実問題があり、中薬の利用が不可避であった状況があり、中薬に対する研究、評価を後押しした。

これに対し、中医の理論の根幹にある五行説に対しては、基本的に肯定的評価は見られないという。確かに宣教師のなかには、五行説の利用を重視する者もいたが、それはあくまで「用語の借用」の次元にとどまり、中医の医学理論としての有効性を真に認めた証拠というより、むしろ中国人患者を警戒させないための実践的工夫といえる。西医と中医の交流を説く宣教師にしても、その言説における「科学的な」西医/「経験主義の」中医といった区別には、自らの西洋近代医学の科学性に対する絶大な信頼が透けて見える。この信頼は、中国医学の歴史を停滞的に捉える見方と表裏一体であった。特に興味深いのは、ある医療宣教師が、患者への配慮から中医に倣い脈診のふりをしたが、みたのが片手の脈のみだった(両手の各脈が各臓器に対応するという)ため、患者らから「医学のことを半分しか知らない」と責められた事例である。この経験から、当該の宣教師は中医理解の必要性を痛感したが、だからといって彼が脈診の有効性を認めたわけではないという。
以上、曺氏が詳細に紹介した近代医療宣教師の事例は、近代化に対する伝統の干渉が、思想の次元と実践の次元で全く様子を異にする可能性を示唆しており、非常に興味深い。もう一つ重要と思われるのは、医療宣教師を捉えていた中国科学停滞説である。第三報告で取り上げた18世紀の事例では、非常に限定的ではあるが、科学の進歩に寄与し得るものが中国に見出された。但し18世紀当時のヨーロッパでは、既に中国科学停滞説がかなり普及しており、18世紀のアミオによる議論はそうした説に対する反論としての役割も帯びていた。そしてこのような学説は、ニーダム問題(Needham Question)に顕著な如く、最近まで勢力を保っている。しかし私が特に注目すべきと思うのは、そもそも中国科学の進歩/停滞をめぐる議論は、中国における「科学」の存在を前提として初めて成立するという点である(存在しないものを批判することはできない)。中国における「科学的なるもの」の発見である。この点において、中国の「科学」は近代西洋の眼差しによって「創造」されたといえるかもしれない。そしてその背景には、「科学」の普遍性に対する信頼が横たわっている。
会の最後を飾る第五報告は、久保茉莉子氏(東京大学)の「中華民国刑事訴訟法の制定と自訴制度」である。久保氏の研究は、私の専門から比較的遠く、内容を把握するだけでも非常に困難であったことをここに自白する。しかし久保氏の研究は、近代中国における法整備の歴史を、近代/伝統の衝突/調和といった単純な図式では捉えきれない、当時の中国の実情との対話の過程として読み解くものであり、この点において今回のワークショップに不可欠なものという確信があった。その確信に違わず、今回の報告も「実情」の複雑さを十分反映した内容であったと感じた。

今回久保報告が取り上げたのは、中華民国において1920年代以降段階的に整備されていった「私訴」もしくは「自訴」=私人訴追制度である。これは「公訴」と異なり、国家的刑罰権を国家機関=検察官によらず、私人=被害者に行使させる制度だという。久保氏によれば、自訴をめぐっては、これまで公訴制度=検察機関による訴追が十分に機能しない当時の状況を、中国伝統法における旧制をもって補ったとする解釈が施され、また刑訴法修正によって自訴の範囲が拡張されたことが強調される傾向にあった。これらの見解に対し、まず自訴制度が特にドイツ刑訴法を参照しつつ、「人民の法律概念が未発達であるため」などといった理由のもと、自訴がもたらす弊害を予防するための様々な細かい規定が、新たに付加されたことを明らかにした。また刑訴法修正の過程において、確かに自訴の範囲は拡大されたが、肝心の科刑判決を獲得する可能性は非常に低かったという。実際の訴訟案件からも、裁判を掌る側における、自訴に対する慎重な態度が看取される。さらに、自訴事件に対する検察の関与が法整備の過程で明確化されたことは、将来的に国家訴追制度の完全実施が目指されたことを暗示する。
以上の事実から、中華民国期における自訴制度とは、決して伝統からの単純な継承物とも、近代西洋の模倣ともいえず、まさに当時の中国独自の実情をその都度反映させつつ確立された、という結論が引き出された。この結論そのものが本ワークショップにとって示唆に富むばかりでなく、久保氏が紹介した事例も大変味わい深い。それはある一般の民間人が、民事訴訟⇒自訴⇒刑事訴訟⇒公訴事件、という実に派手な訴訟行動を行ったことを示す事例である。この訴訟人は、自らの利益増大を狙って、より有利な形態の訴訟に切り替えることを繰り返した。久保氏の述べる如く、「当時の人々が法律の規定を巧みに利用して利益を勝ち取ろうとしていた一面をうかがうことのできる例」といえよう。恐らく、国家の側が「人民の法律概念が未発達である」≠前近代的というレッテルを貼って警戒したのは、こうした一般民衆における驚くべきしたたかさであり、それは時として伝統/近代といった観念的図式など軽々と乗り越えてしまう力強さを発揮することを思い知らされた。
以上が第二部の概略である。実は第二部を構成するにあたって、当初掲げたのは、中国の近代/西洋化が、実際には伝統の持つ強靭な合理性との相克/相生によって形成された、といういわば図式的すぎる図式だった。上の報告に明らかな如く、この図式は二人の報告者によって見事にかわされる形となった。第一部と第二部を通して、非常に刺激に富む議論を交わしてくれた全報告者に改めて感謝したい。
最後にCPAG代表の中島隆博教授が述べた如く、「迂回しつつ」繰り返し問い直す、そういう方法で「新しい普遍」への挑戦を、私なりに担っていければと思う。


報告:新居洋子(CPAG特任研究員)